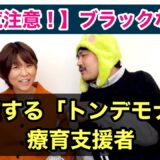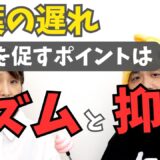療育では、「苦手な感覚があれば、慣れさせていきます」と言われることもあるかもしれませんが、医学的に見て「それは、あり得ない話」です。
なぜなら、苦手な感覚がなぜ苦手か、というと、そこに意味はないからです。
つまり、脳が苦手と感じるから、という以外に理由はないのです。
嫌なものは、イヤ!
それだけです。感情論ではありません。医学的見地から、そう言えるのです。
もし、それをイヤじゃないようにしようとするなら、脳神経のつながり(ネットワーク)を変えるしかないです。
しかし残念ながら、今の医学では、脳神経のネットワーク(つながり)を、薬や手術で変えることはできません。
つまり、医学的にそれは、非現実的ということです。
ですが、ここで裏話。
イヤな感覚刺激のある遊びを、イヤと言わせない簡単な方法があります。
それは「子どもを、怖がらせる」という方法です。
「イヤだ」というと、叱られる。お尻を叩かれる。皆頑張っているよと言われる、学校に上がったら、そんなわがままを言えなくなるよと言われる、そんな療育もあります。
所謂、やる気があればできるから頑張らせる、論です。
さて、そんなことを繰り返していると、どうなるか?
子どもはだんだん「イヤだ」という主張をしなくなります(誤学習をしてしまうわけですね)。
イヤだと言わなくなる代わりに、意志の表出が減ります。
そうなると、「おとなしくなった」「我慢ができるようになった」と勘違いされます。
そして、「やっぱり療育では、厳しく接した方が、子どものためになるんだ」と勘違いする保護者が生まれます。
いわゆる負のループが起こります。
やがて子どもは主張することを止めていき、いわゆる「やりやすい子」になっていきます。
なにせ大人が怖いから。
そして、体が大きくなってきたときに、鬱屈したエネルギーが爆発します。
爆発するとは、「かつて自分がされたことと同じようなことをする」です。
つまり、力で押さえつけられてきた子どもは、自分の力にまかせて他者(親御さんも含む)を押さえつけようとします。または、暴力を使って反抗しはじめます。
「人に言うことを聞かせるためには、怒鳴ったり、叱ったり、暴力をふるえばいい」と思い、そのように行動します。かつて自分がそうされたように(この事例は本当に多いです)。
そして、子どもの心も家庭も、崩壊します。
もちろん、子どもは加害者ではなく、被害者ですよね。
親御さんは、「苦手なことを克服させる療育」を選んでしまった、という意味では一部責任があります。
ゆずが、なぜこれほどまでに「克服させる療育」について警鐘を鳴らしているかというと、今幼児期を過ごしている保護者の方に「あの時、気付いていれば・・・」と思ってほしくないからです。
手遅れになる前に、気付いてほしいからです。
定型発達に合わせる、というなんの医学的根拠もないことに、エネルギーを使わないでいただきたいからです。
後悔先に立たず。
せっかくご縁があって、私たちのサービスを利用してくださっている方々(このブログを読んでくださっている方も)に、後悔してほしくないです。
また、こども発達LABO.のYouTubeチャンネルにも「幼児期にもう少し正しい知識を持って療育を選べば良かった」「今から戻れないですよね」といったコメントをいただくことがあります。
残念ながら、戻れません(当たり前のことですが)。
こういった先輩保護者の生の声を、ぜひ参考にして、「今、この子に、何が必要か」ということを考えてあげてください。
「子どもを変えます!」「できないことをできるようにします!」という魅力的な療育があれば、盲信するのではなく「その根拠は?」と、常に検証する習慣を持ってください。
それが、将来の「こんなはずではなかった」を防ぐ最大の方法になります。
動画でも繰り返しお話していますが、大切なのは「子どもを変えること」ではなく、今の子どもの状況を理解してあげること、そして工夫してあげること、です。
だから、感覚の特性を「変える」ような取り組みをするべきではないのです。
子どもは大人(または親)の付属物ではありません。コントロールする対象ではありません。
一人の人間として思うことを主張することができ、その主張に対して大人はできるだけ配慮してあげるという姿勢が必要です。
子どもには療育プログラムを、あるいは療育そのものを拒否する権利があります。
拒否されたら、叱るのではなく、叩くのではなく、「どうすれば気分良く遂行してもらえるか」という方法を考え、実践する。
叱ったり叩いたりしなくても、上手くいくやり方があります。
「この子のために、私が厳しくしなければ」と思い、敢えて心を鬼にしている、といった保護者の方もおられるかもしれません。
でも本当は「我が子を大切に育てたい」「我が子の笑顔をもっとみたい」と願っているに違いないです。
大丈夫です。
敢えて心を鬼にする必要なんかありません。
お子さんの「特性の理由」を正しく理解するだけで、手立てが見え、お子さんの発達を最大に引き出しながら、笑顔で子育てができるようになります。
だからこそ「我が子の特性の理由を知らない」なら、ゆずの療育の中で、我が子の特性の理由を学んでください。
我が子を今以上に理解できたとき「辛い子育て」が終わり、「ワクワクする子育て」が始まります。
 親子で学べる療育教室 発達支援ゆず
親子で学べる療育教室 発達支援ゆず